競合模倣対策室
オリゴ糖食品事件
- 原告
- 当社
- 被告
- 株式会社はぐくみプラス
- 結果
- 勝訴
- 裁判に関する情報
- 問題となった行為
-
①被告商品であるオリゴ糖食品『はぐくみオリゴ』の広告にて「オリゴ糖100%」等事実と異なる成分表記をした行為(以下、「(①)」)
②イベントで、当社商品であるオリゴ糖食品『カイテキオリゴ』よりも被告商品の方がオリゴ糖の含有量が多い旨の発言をした行為(以下、「(②)」)
- 第一審 事件概要
-
はぐくみプラス社は、自社商品であるオリゴ糖食品『はぐくみオリゴ』の広告にて、オリゴ糖の成分が53.29%であるにもかかわらず「オリゴ糖100%」等、商品の内容を誤認させるような表示をしていました(①)。
さらに、はぐくみプラス社は、アフィリエーター向けのイベントにおいて、実際には当社商品『カイテキオリゴ』の方がオリゴ糖を多く含んでいたにもかかわらず、「『はぐくみオリゴ』の方がオリゴ糖の含有量が多い」等、当社商品が不利になるような説明を行いました(②)。
当社は、①の行為が不正競争防止法上の品質誤認表示に該当し、また、②の行為が同法上の信用毀損行為に該当するとして、損害賠償請求訴訟を提起しました。
- 第一審 判決の概要
-
●認定
裁判所により、はぐくみプラス社の被告商品広告にて「オリゴ糖100%」等事実と異なる成分表記をした行為(①)が品質誤認表示として認められました。
一方で、イベントでの虚偽の発言(②)は、信用毀損行為として認められませんでした。
●裁判所の命令
はぐくみプラス社に対し、合計金18,357,803円及びこれに対する遅延損害金の支払いが命じられました。
●判決に対する対応
イベントでの虚偽の発言(②)については、信用毀損行為として認められず、また、認容損害額が当社の損害に満たなかったため、控訴しました。
- 第二審 事件概要
- イベントでの虚偽の発言(②)について、不正競争防止法における信用毀損行為に該当するとして、控訴しました。
また、第一審により認められた「事実と異なる成分表記(①)」についても併せて審理されました。
- 第二審 判決の概要
-
●認定
裁判所により、はぐくみプラス社の
・被告商品広告にて「オリゴ糖100%」等事実と異なる成分表記をした行為(①)
・イベントで「『カイテキオリゴ』よりも被告商品の方がオリゴ糖の含有量が多い」旨の発言をした行為(②)
に対し、①には品質誤認表示が、②には信用毀損行為が、それぞれ認められました。
●裁判所の命令
はぐくみプラス社に対し、遅延損害金含む合計金82,262,000円の支払いが命じられました。
- 判決のポイント
-
【問題となった行為①】
第一審では、はぐくみプラス社によるイベントでの発言について信用毀損行為は認められず、当社としてはこの判断に異議があったため、知的財産高等裁判所に控訴いたしました。
この結果、第二審では信用毀損行為が認められるとともに、損害額が第一審の約3倍の金額である68,900,853円と認定され、当社は、はぐくみプラス社から遅延損害金含む合計金82,262,000円の支払いを受けました。
当社は今後も、合理的ではないと考える判決に対して、納得できるまで争う姿勢で取り組んでまいります。
【問題となった行為①・②】
本件では、アフィリエーターの行為についても、広告主であるはぐくみプラス社の行為として認められたことにも意味がある判決となりました。なお、当社は、本件ではアフィリエーターに対して不正競争防止法違反を主張しませんでしたが、目元用アイクリーム事件では、広告主だけではなく、広告代理店に対しても当社への信用毀損行為を主張し、結果として広告代理店にも不正競争行為及び当社への不法行為が認められました。
当社では、広告代理店やアフィリエーターに対しても、事案に応じて責任を問うべきか否かを検討し、厳しく対応していく所存です。
【損害額】
「損害額」は、損害を受けた側(原告側)が証拠に基づき、権利侵害行為と損害額の因果関係を「証明」しなければならず、その因果関係の証明は、難易度が高いため、損害賠償請求が認められない、または、認められたとしてもその金額が高額となることは多くありませんでした。
本件は、原告(控訴人)が「不正競争防止法5条2項」に基づく主張をしたところ、これが認められ、はぐくみプラス社の違法表示による損害額の算定が、「不正競争防止法5条2項」に基づき算定されることとなりました。「不正競争防止法5条2項」による損害額の算定方式は、損害を与えた側(被告側)の「利益の全額」を損害額と推定し、そこから被告側が「侵害者(被告側)による侵害行為と無関係な利益部分」を証明し、損害額を覆滅していくというものです。これは被告側の利益の全てが損害額であるという前提に立つため、被告は証明に失敗すると、被告の利益の大半を原告に支払わなければならないということになります。
本事件のように違法な表示行為等を行った場合には、高額な損害賠償命令が下りる可能性があります。
- 参考文献
- ・年報知的財産法2022-2023
「2022年判例の動向 判例の動き Ⅲ不正競争防止法 3不正競争防止法第2条1項21号」
年報知的財産法2022-2023 92-93頁 日本評論社
・弁護士 井﨑 康孝(2022)
「新判決例研究(第356回)オリゴ糖の純度に関する表示及び発言が品質誤認表示(不正競争防止法2条1項20号)及び信用棄損(同項21号)に該当するとして損害賠償請求が認められた事案[知的財産高等裁判所令和4.1.27]」
『知財ぷりずむ : 知的財産情報』20巻 12-18頁 発明推進協会
・弁護士・弁理士 高橋 正憲(2021)
「ネットビジネスにおける広告表示の違法性について(1)」
知財弁護士.com(閲覧日:2024年9月24日)
・弁護士・弁理士 高橋 正憲(2021)
「ネットビジネスにおける広告表示の違法性について(2)〔アフィリエーター広告の違法性〕」
知財弁護士.com(閲覧日:2024年9月27日)
・弁護士・弁理士 高橋 正憲(2021)
「ネットビジネスにおける広告表示の違法性について(3)〔品質誤認表示の損害賠償〕」
知財弁護士.com(閲覧日:2024年9月27日)
・通販新聞(2020)
「北の達人コーポレーション 不競法で差止請求、はぐくみプラスのLINE広告」
通販新聞(閲覧日:2024年9月24日)
目元用クリーム事件
<開示請求>
- 原告
- 当社
- 被告
- エックスサーバー株式会社
- 結果
- 勝訴
<本訴(損害賠償等請求事件)>
- 原告
- 当社
- 被告
- 株式会社キーリー、株式会社リトルギア
- 結果
- 勝訴
- 裁判に関する情報
- 問題となった行為
-
①根拠に基づかないランキング1位の表示をした行為(以下、「①」)
②当社に関する下記のような虚偽の記載をした行為(以下、「②」)
・当社商品は返品及び中途解約ができない旨の記載
・当社商品に関する誤った金額の記載
- 事件概要
- <開示請求>
当社は、根拠に基づかないランキング表示(①)及び虚偽の記載(②)が不正競争行為に該当することを理由に損害賠償請求をすべく、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者の開示を請求しました。
<損害賠償請求>
当社が販売するアイクリーム『アイキララ』と競合するアイクリーム『Memorich(メモリッチ)』を販売するキーリー社が、広告代理店であるリトルギア社に虚偽の内容が含まれる比較広告及び公式販売サイトを制作させ、公開させました。
キーリー社は、自身の販売する『Memorich(メモリッチ)』の公式販売サイトにて、
・モニターが選んだアイクリームランキング1位
・目元の悩みに使ってよかったアイクリームランキング1位
・目元に優しい化粧品アイクリームランキング1位
と、裏付けや根拠に基づかないランキング1位の表示をしていました(①)。
※キーリー社による根拠に基づかないランキング表示また、リトルギア社のWebサイトに公開された比較広告では、 『アイキララ』の価格が実際の価格よりも高く表示されるなど、 当社に不利な虚偽の内容が表示される一方で、キーリー社に有利な内容が掲載されていました(②)。
※リトルギア社による当社商品に関する虚偽情報を内容とした表示これらを受け当社は、キーリー社と、キーリー社から依頼を受け虚偽の比較広告とランキング表示を制作したリトルギア社に対し、 不正競争防止法に基づき、損害賠償請求訴訟を提起しました。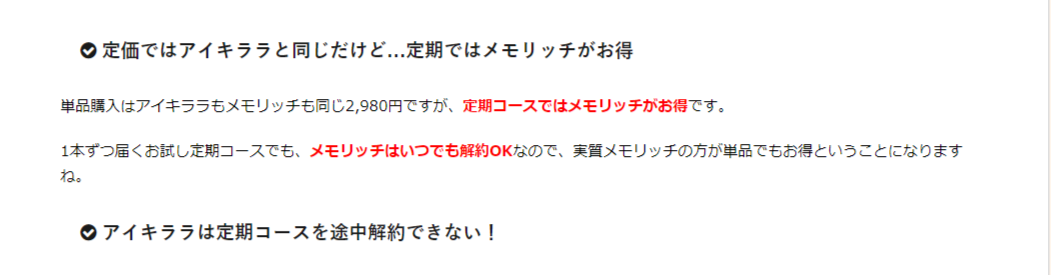
- 判決の概要
-
<開示請求>
当社による開示請求が認められました。
<損害賠償請求>
●認定
裁判所により、キーリー社とリトルギア社の
・根拠に基づかないランキング1位の表示をした行為(①)
・当社商品に関する虚偽の内容を記載した行為(②)
に対し、品質誤認表示(①)、一般不法行為(②)がそれぞれ認められました。
●裁判所の命令
キーリー社とリトルギア社に対し、当社の被った損害額及びこれに対する遅延損害金の支払いが命じられました。
- 判決のポイント
- <開示請求>
開示請求により、虚偽の内容が含まれる比較広告を公開していた広告代理店であるリトルギア社の代表者と『Memorich(メモリッチ)』を販売していたキーリー社の代表者が同一であることが判明しました。
そのため、当社は、キーリー社がリトルギア社を隠れ蓑として比較広告を公開したと考え、リトルギア社のみならずキーリー社にも損害賠償請求を行いました。
当社では日々不当な広告の表示がないか巡回しており、違法行為を発見次第、行為者の特定を進めております。
当社では、今後とも、不当な広告表示に対して、発信者が匿名であっても開示請求等により必ず特定し、お客様が当社の商品を安心してご購入いただけるよう対応してまいります。
<損害賠償請求訴訟>
【問題となった行為①】
根拠に基づかないランキング1位表示が「品質誤認表示」に該当することが認められた画期的な事案となりました。
景品表示法を根拠として行政から問題視されることの多いランキング表示ですが、当社は、本件のような業界に不信感を与える行為についても、市場の安心・安全のために、不正競争防止法を用いて厳しく対処いたします。
【問題となった行為②】
本件においては、知的財産法が適用されず為す術がなかった不正な行為について、最高裁判決(※)以後日本で初めて、民法上の不法行為が認められました。
※「北朝鮮映画事件」平成21(受)602、最一小判平成23年12月8日。著作権法上保護されない映画の利用について、民法上の不法行為が否定された事案。
当社は今後も、過去事例の判断にかかわらず、当社が問題であると考える行為について、積極的に取り上げ、厳格に対処いたします。
また、当社は、インターネット上に公開されている当社商品の誤った情報により、お客様にご心配をおかけしないためにも、日々の巡回を継続してまいります。
【問題となった行為①・②】
①・②ともに、 実際にインターネット上に公開したのはリトルギア社でしたが、キーリー社とリトルギア社の代表取締役が共通していることに加え、①についてはキーリー社が『Memorich(メモリッチ)』の販売主体(営業主体)であること、②については業務委託関係があること等を理由に、キーリー社とリトルギア社の双方に不正競争行為が認められました。
当社では、実際の行為主体が異なることから、一見すると不正競争行為を行っていないように思える主体についても、実質的な状況を調査し、悪質性が高いと考えた場合には、厳しく対応してまいります。
- 参考文献
- ・経済法令研究会(2024)
「重要判例紹介 1商品広告におけるランキング表示が、不正競争防止法2条1項20号所定の品質誤認表示に当たるとされた事例 2商品の比較広告が、不正競争防止法2条1項21号所定の信用毀損行為には当たらないが、民法上の一般不法行為に当たるとして、損害賠償責任が認められた事例」
『金融・商事判例』通号1696 26頁 経済法令研究会
・通販新聞(2021)
「北の達人コーポレーション キーリーを提訴、不競法違反で損害賠償1億円」
通販新聞(閲覧日:2024年9月24日)
足用消臭クリーム事件
- 原告
- 当社
- 被告
- upscript合同会社
- 結果
- 勝訴
- 裁判に関する情報
- 問題となった行為
- ①後述する当社イラストを模倣した行為
②当該イラストを模倣したイラストを被告商品の広告ページに使用した行為
- 事件概要
-
upscript社は、当社が販売する足用消臭クリーム『NO!NO!SMELL(ノーノースメル)』と同種の商品である『WILL CLENS(ウィルクレンズ)フットデオドラントクリーム』及び『WILL CLENS(ウィルクレンズ)シューズデオドラントパウダー』を販売していました。
upscript社は、自社商品の広告ページにおいて、当社広告画像(※1)に描かれた靴を履いた足の状態を表したイラスト等が描かれた広告画像(※2)を掲載していました。
このため、当社は、upscript社に対して著作権及び著作者人格権の侵害訴訟を提起しました。
※1 当社広告画像※2 upscript社広告画像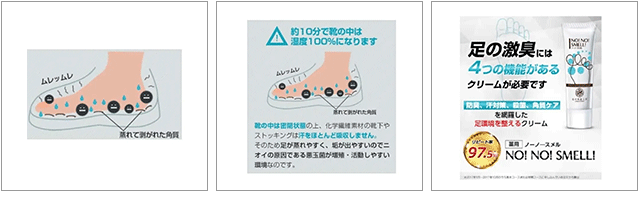
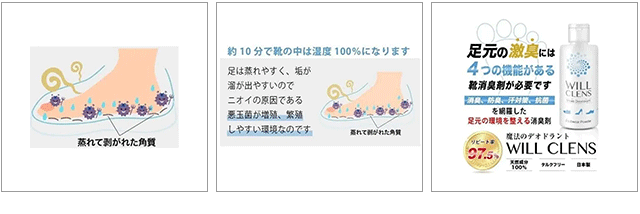
- 判決の概要
- ●認定
裁判所により、upscript社の
・上述の当社イラストを模倣した行為(①)
・当該イラストを模倣したイラストを広告ページに使用した行為(②)
に対し、著作権及び著作者人格権の侵害が認められました。
●裁判所の命令
upscript社に対し、
・損害賠償金の支払い
・慰謝料の支払い
・upscript社が広告ページに使用した模倣イラストの削除
・upscript社が保有する模倣イラストデータの削除
が命じられました。
- 判決のポイント
-
【問題となった行為①・②】
本件のようにシンプルなイラストの模倣は、過去の判例・裁判例では、著作権等の侵害が認められていませんでした。
(参考:「釣りゲーム事件」 平成24(ネ)10027、知財高判 平成24年8月8日)
しかし、当社としては、当社商品のお客様や当社商品に興味を持ってくださった方々が安心して購入したい商品を選択できるように、本件のような模倣行為を見過ごすことはできないため、過去の判例や既成概念にとらわれず、社内メンバー・社外専門家が一丸となって訴訟戦略を練り、裁判所からupscrip社による当社イラストの模倣行為(著作権侵害行為)があったと認められました。
- 参考文献



